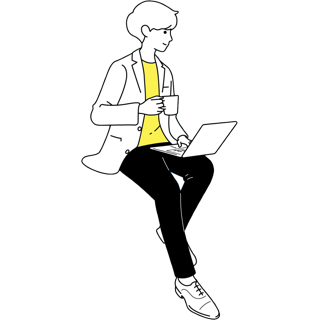「地元のネガティヴ面が気になりすぎてモヤモヤする」の相談内容詳細
-
いまストレスを感じている「出来事」を事実ベースで抜き出してみてね。
「いつ・どこで・誰が・何を」を意識するのがコツだよ。
- 数年前から今の住んでる地元が廃れる、荒れている様に耐えられない。
地元では事件や経済とか県や市や町の政治不信、地元のお店もコロナ渦でどんどん閉店したりと良いことが全然無い。
同じ地元の人の話やSNSのつぶやきを見ても、地元のマイナス面の事が気になりすぎている。
かといって私情により他県に引っ越すことは難しい状況です。 - 「1」についての「感情」を%で表現してみてね。合計で100%にならなくても大丈夫。直感で書いてみよう。
- 悲しみ80%怒り90%不安80%
- 「1」について浮かんでいる「考え」を教えてね。
- 自分は、ずっと慣れてきた地元がなんだかんだ好きだ。
確かに地元は日本でも田舎の県で魅力的なモノや観光地や食べ物も少ない、そこに地元のトップの人たちはじめ地元の人たちが様々な問題を起こしたり政治的にも意見が分かれて人々の心はばらばらになり大荒れの状況なっていて苦しい。
地元の大きなお祭りもあるが、お祭り会場周りの町の景色はシャッターが増えたり、地元の人たちもネガティブな事しか言わない、そんな光景や話題に自分は過敏に反応してしまう。
ただ、慣れてしまったゆえに急に変えるのはもう年齢的にも難しい。
それに自分は、35歳で精神障害とうつも持っていて、実家暮らしで障がい者雇用でやっと働いていけてる。
今から都会に引っ越して新しい職を探すのは非常に困難どころか絶望的だ。
実家は実家で65歳になった父母が気になる。近い将来親の介護も始まるかもしれないのに引っ越して大丈夫だろうか。ほかに兄弟はいない状況だ。 - いろんな視点から捉えるために、上記の回答の「別の可能性」を考えてみよう。
- 仮に引っ越すとしたら、障がい者雇用で生きてきた自分はどう生きていけばいいのか。
他県や田舎と反対の都会に引っ越したら地元のうやむやに振り回されずに平和に暮らせれるかどうか。
地元のいいところに目を向ける、地元で良好な人間関係を作れればまだ希望はあるのではなかろうか。 - いま専門家に聞いてみたいことは?
- こんな自分ですが、他県に引っ越すか地元で生き続けていくかどうしたらいいですか?地元で生きるにはどういった工夫をすればプラス思考で生きていけますか?
- 年齢、性別、職業
- 35歳 男性 障がい者雇用(アルバイト)
- 既往歴
- うつ、精神障害、発達障害(ADHD)、中度HSP
- 悩みの内容の自由記述
- --- 未回答 ---
自分史はまだありません。
※ プライバシー保護のため、ご質問の一部を編集部で変更している場合がございます。
「地元のネガティヴ面が気になりすぎてモヤモヤする」への回答
-
KD さん、ご相談を寄せていただきありがとうございます。精神保健福祉士の中浦です。
慣れ親しんだ地元の経済状況が芳しくないことや、その影響によって悲観的な雰囲気を KD さんが感じてモヤモヤしてしまうのですね。地方都市の活性化は KD さんの地元だけでなく日本全体の大きな課題だと思います。
また、精神疾患があることで選択や行動に制限があるという状況も、地元の荒廃だけでなく生活や考え方に苦しさや窮屈さが生まれる原因でもあるように感じています。
【聞いてみたいこと】には以下の2つが記載されていましたね。
①他県に引っ越すか地元で生き続けていくかどうしたらいいですか?
②地元で生きるにはどういった工夫をすればプラス思考で生きていけますか?KD さんの今後の行動や普段の考え方に役立つアドバイスができるよう考えていきたいと思います。
障害者雇用は都会の方が進んでいる
①の他県に引っ越すか地元に居続けるかについてですが、相談内容に『自分は35歳で精神障害とうつも持っていて、(中略)。今から都会に引っ越して新しい職を探すのは非常に困難どころか絶望的だ』と書かれていたので、まずは都会に出て職を得ることについて正確な情報を知ることから始めましょう。特に客観的なデータは感情的な疑いや不安を変化させるのに役立ちます。
「都会に出て職を探すのは困難だ」ということですが、厚生労働省が公表しているデータによると、障害者雇用は都会の方がはるかに進んでいるようです。例えばですが、