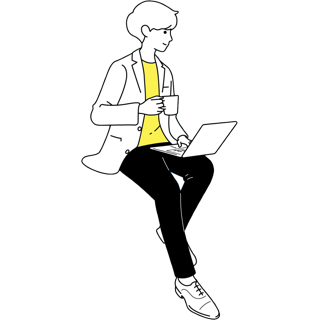「発達障害の診断との向き合い方がわからず、生きづらさを感じます」の相談内容詳細
-
いまストレスを感じている「出来事」を事実ベースで抜き出してみてね。
「いつ・どこで・誰が・何を」を意識するのがコツだよ。
- ASDと診断されたことで自分のことが全く分からなくなり、更に自信がなくなった。
かかりつけの心療内科の主治医にASDじゃないかと言われたものの、ここでは詳しい診断はできないから、希望するなら別のところへ行ってくれと言われた。
中途半端にそのワードを出されたことで、自分で勝手に過去の言動を逐一振り返って答え合わせをし始めてしまって、歯止めがきかない。
結果、自分が更に分からなくなったし、現在の自分の言動にも完全に自信がなくなって、対人関係が更に怖くなった。
・普段から人の目を見て会話していたはずだけど、ちゃんと出来ているか逐一気になるようになった。
会話をしながら、今自分はこの人の気持ちを理解しているのか、おかしな発言をしていないか、等と考え出したら、常に正解を探すようになって、余計に対人関係が辛くなってきた。
・ASDの要素とされるような性格を持ち合わせていることは自覚しているが、今までは全て家庭環境が原因で後天的に構築されたものだと思っていた。
診断されてからというもの、過去の振り返りが辞められなくなってしまい、自分がますます分からなくなってしまった。
・没頭するような趣味はある。
でも私のそれは周りの人と違って障害特有のこだわりなのだと言われたら、何だか悲しいし、アイデンティティが無くなった気分。
主治医には1年程診察を受けているので、単なる思い付きの発言ではなさそうなことも、複雑な気持ちの理由。
お金を払って精密に検査をしたら気が楽になるのかどうかも自信がない。
あなたはASDじゃないですよと言われたいだけのかもしれない。
ただこの終わりのない自問自答を辞めたい。
出口のない苦しさから解放されたい。 - 「1」についての「感情」を%で表現してみてね。合計で100%にならなくても大丈夫。直感で書いてみよう。
- 虚しさ100% 自己嫌悪80% 困惑80% 悲しさ60%
- 「1」について浮かんでいる「考え」を教えてね。
- 自分の体臭に気づきにくいように、言動も他者から見た方がおかしさに気づくのだろうと思う。
だから、あなたは他人の気持ちが理解できないと言われてしまったら、そうなんだと受け入れるしかない。自分は理解できているだなんて断言できるはずがない。
相手の気持ちを分かっていると思っていても、それは間違っているんだろう。
ASDの特性は家庭環境とは関係がないと読んだ。
自分がASDなら、今まで自分の思考の偏りの原因だと思っていた家族は関係なかったことになるので、更に自己嫌悪に陥る。
生まれた時からおかしかったという結論には虚しさを覚える。
ネガティブな思考を切り離せなかったり、家庭環境など過去のことをいつまでも引きずっているのも、ASDだからなのかもしれない。 - いろんな視点から捉えるために、上記の回答の「別の可能性」を考えてみよう。
- 確かに昔から日常でストレスを感じることはあったから、それが原因だと考えたら、気が楽になる気もする。
過去を振り返って自分の言動を確かめようとするのは、単に診断を受け入れられないだけなんじゃないのか。素直に受け入れてしまった方が全て楽になるのではないか。 - いま専門家に聞いてみたいことは?
- 発達障害の診断が下りて安心したという人は多くいることを知っていたけれど、私は余計に困惑し、更に生き辛く感じてしまいました。
とはいえ、自分の言動で無自覚のうちに他人を不愉快にし続けているとしたら、自覚できた方が楽かもしれないとも思います。
この診断をどのように受け止めれば気が楽になるのか、また詳しい診断を受けるべきか、教えていただきたいです。 - 年齢、性別、職業
- 20代 女性 会社員
- 既往歴
- 鬱で4年ほど通院しています。
- 悩みの内容の自由記述
- ・大学時代、教授が突然PCでしか作れない課題を出して、欠席した人も当日中に提出しなければ単位をあげないと言った。
こういった発言やメールは多く、精神的に振り回されたけど、周りの子は冗談でしょwと気に留めていなかった。
家族に理不尽な事を要求され、従わなければ前にくれたものを返すよう言われたり、何かをお願いしたらわざとやってくれなくなった経験から、教授の言動が冗談に思えなかった。
今の解釈
→ASDだから単に冗談が分からなかった
・完璧主義。例えば昼食を買う時、値段を逐一チェックして、少しでも安いものを買おうとする。買った物があまり美味しくなかった時、お金を無駄にした自分にイライラする。
母親が完璧主義者で、小さい頃から自分の物をチェックされて1円単位で無駄を指摘されたり、ちょっとしたミスで全てをやり直しさせられたから、その影響だと思っていた。
今の解釈
→単に先天的なASDの特性では
-
30歳まで
-
26
コロナの影響で転職
新しい職場は前職とは正反対の雰囲気で、明るく挨拶しても2割程度しかまともに挨拶を返してくれない(嫌われてるのではなくそういう空気)
このまま明るくし続けていたら正に「空気の読めてない人間」になるのでは?どうすればいい?どうすればいいか分からない時点でもう普通ではない?
-
-
-
26
迷惑をかけたくない気持ちから自分から人に連絡出来なくなったので、連絡をし続けてきた相手にただ返し続けてたら、なりゆきで彼氏になった。
傷つきたくなかったから惰性の気持ちを保とうとしていたけれど、段々この人を失ったら誰も残らないと怖くなってきた。ちょっとした口論をしただけでSNSを全部ブロックされる悪夢を見た。
-
-
-
24
就職
鬱から抜け出して就職。明るく振る舞おうと頑張っていたのに引き継ぎの人から「何を考えてるか分からなくて不安」と言われた。
私はもう何をどう頑張っても駄目なんだと疲れてしまった。
-
-
-
23
LINEで教授とのやり取りやグループ内の不和が起こる度に精神的に耐えられなくなり、開く時に過呼吸を起こすようになった。大学卒業後、もう誰も自分を必要としてないだろうしLINEを削除した。
私が会話から感じとった"ピリピリした空気"はただの思い込み?妄想?
だってASDなら感受性が無いはずだから
-
-
-
23
就活で本格的に鬱になった。自分の良い所が何も言えなくて面接で何度も泣いた。
就活でとかく謳われていた「人柄重視」という言葉がとても残酷だと思った。自分には中身が何も無いと思ってたし、試験結果や偏差値が自分の価値の尺度だったから、それを否定しないでほしいと思った。
自己PRをしようとする度に、私を馬鹿にして笑う母と兄の顔がチラついた。
-
-
-
21
20人位の大学のグループで一人だけ誕生日を忘れられて、祝ってもらえなかった。抜かされたまま2週目に入ったので耐えられなくてLINEグループを抜けた。
「自分には価値が無い」が可視化された出来事
-
-
20歳まで
-
18
大学入学
社会問題について自分でちゃんと考えて意見を言えるような人間になりたかったから、そういった学問に関係する学部を選んだ。
考えることが好きだった。でも私の思考が歪んでいるのなら、私が何かを考えることに何の意味があったんだろう
-
-
-
15
仲の良いグループの中で一人、自分を露骨に嫌ったり、ある時は極端に馴れ馴れしくしてくる子がいた。
嫌われる事が増えてきた為、私が抜ければこのグループは元通りになると思い、卒業を機に距離を置くようにした。他人には何も期待できないし、自分さえ消えれば全部解決すると思った。
ASDだからコミュニケーション能力が無いと言われてしまったら、これも私が原因だったのかなと思うしかない
-
-
-
15
中学3年のクラス替えで友達全員と離れた。新しいクラスには偶然だろうが既存のグループがもう出来ていたため、迷惑になりたくないから1年間クラス内で一人でいることに決めた。
人に嫌われたくなかったし、自分は一人でも大丈夫だと思った。
これも障害だったと言われたらやるせない
-
-
-
12
1年の最初の学期末試験で学年トップを取ってしまったので、それ以降成績が下がる度に教師や親に「あなたはこんな人じゃない」と叱られた。褒められた記憶が殆どない。
本当の自分は何なんだろうと思った。
今も苦しめられている完璧主義が構築された時期だと思っていた。でも私の完璧主義はASDの特性なら関係ないのかも。
-
-
-
11
兄と母親に難しい問題を出されて分からないと馬鹿にされることが多かった。辛かったので担任に言ったら個人面談で母に伝えられた。母は「馬鹿に馬鹿と言って何が悪い」と激怒してしばらく口を聞いてくれなくなった。
わからない。こんな昔のことまで引きずってるのは頭がおかしいのかもしれない
-
-
-
11
小学校高学年
どうしてかはっきりとは分からないけど、この時点で
・自分は周りの子達より価値が無いから、勉強を頑張って埋め合わせしよう
・自分は何をされても言われても大丈夫な人だから、他の人の事を優先しよう
この2点をはっきりとポジティブに自覚していたことは覚えてる。この頃から自己肯定感の無さが顕在していた。
これがただの先天的な障害だったというのなら私は一体何なんだろう
-
※ プライバシー保護のため、ご質問の一部を編集部で変更している場合がございます。
「発達障害の診断との向き合い方がわからず、生きづらさを感じます」への回答
-
リサ さん、ご相談をよせてくださりありがとうございます。臨床心理士・公認心理師の小野寺です。
まずはお断りをさせてください。 リサ さんは今回のご相談を含めて2件ご相談を寄せてくださっていますね。
中でも リサ さんにとっては「2件目の方が重要度が高い」とのことでしたので、2件目を中心にお返事させていただきます。1件目に関しては、今回のお返事に関係するところを部分部分ピックアップする形に致しました。ご了承ください。
そしてもう一つお断りです。「かかりつけの心療内科の主治医にASDじゃないかと言われたものの、ここでは詳しい診断はできない」と言われたのですね。だとすると、この主治医の指摘は「診断された」というレベルではないように思います。
しかし、 リサ さんご自身の感覚としては「ASDと診断された」と言えるくらいの衝撃でしたよね。ですので、今回は リサ さんの記述にそって「診断」という言葉を私も使わせていただくことにしました。この点もご了承ください。
さて、 リサ さんは今「発達障害との診断をどのように受け止めれば気が楽になるのか、また詳しい診断を受けるべきか」を悩んでおられるのですね。
リサ さんが発達障害の診断を受け止めきれない主な理由は「今まで自分の思考の偏りの原因だと思っていた家族は関係なかったことになる」「今までは全て家庭環境が原因で後天的に構築されたものだと思っていたが、それは違うのではないか」と思えるからなのだと想像します。
つまり、「兄と母親に馬鹿にされることが多かった」ゆえに「考え方の歪み」が生じたと思っていたけれど、実は生まれつき考え方が歪んでいたのではないか。そのように思われて、あたかも自分に責任があるかのように感じられてお辛いですよね。
「馬鹿に馬鹿と言って何が悪い」と激怒し、しばらく口を聞いてくれなくなるようなお母様ですから、 リサ さんとしても相当思うところはあるかと思います。
それなのに、発達障害(ASD)と診断されてしまって、なんだか「お母さんは悪くない。悪いのはあなた自身」と言われたような気がしておられるのではないでしょうか。そのせいで リサ さんはご自身を責めておられませんか? とても心配しております。
診断は受けなくてもいい
ここまでのところを踏まえ「詳しい診断を受けるべきか」について私の見解をお伝えさせていただきます。私は「診断を受けなくてもいいのではないか」と思います。
リサ さんは発達障害(ASD)を自責のためのスティグマと感じられている印象を強く受けたからです。