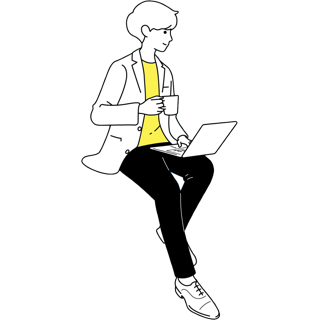「病気が怖すぎる。もしなったら諦めが肝心ですか?」の相談内容詳細
-
いまストレスを感じている「出来事」を事実ベースで抜き出してみてね。
「いつ・どこで・誰が・何を」を意識するのがコツだよ。
- 病気が怖いです
当たり前に過ごせてることにありがたみを感じている反面ガンや病気でおじゃんになると思うとなんで死ぬまでこんなこと考えないといけないんだと思ってしまう - 「1」についての「感情」を%で表現してみてね。合計で100%にならなくても大丈夫。直感で書いてみよう。
- 不安100
- 「1」について浮かんでいる「考え」を教えてね。
- 年を取ると死に近づくので病気になりやすくなるので長生きしたくない
楽に死ねる薬があるなら病気も怖くないんだけど - いろんな視点から捉えるために、上記の回答の「別の可能性」を考えてみよう。
- 事故で死ぬかもしれない、いつか突然終わるかもしれない
ニュースで事故を見るたび具合悪い - いま専門家に聞いてみたいことは?
- 避けられない不幸に対する考え方、教えてほしいです
なったときは諦めが肝心ですか - 年齢、性別、職業
- 26
- 既往歴
- --- 未回答 ---
- 悩みの内容の自由記述
- --- 未回答 ---
自分史はまだありません。
※ プライバシー保護のため、ご質問の一部を編集部で変更している場合がございます。
「病気が怖すぎる。もしなったら諦めが肝心ですか?」への回答
-
さん、ご相談を寄せていただきありがとうございます。精神保健福祉士の中浦です。
『病気が怖い』とのご相談ですね。病気は苦しみを伴ったり生活に変化をもたらしたりするので、怖さや不安も大きいですよね。
その中で、私が さんが感じる病気への恐怖の特徴に、徐々に何かが失われたり変化することに対する不安があるのではないかなと感じています。なぜなら、 さんは「死」を恐れているわけではなさそうだからです。
病気を恐れる人の多くは、病気の先にある死を恐れていることが多いと思います。実際死がどのようなものかは私にもわかりませんが、残されたものから見る死は、ある人の存在を失う喪失体験です。一方、病気はその人の存在が喪失してしまうまでの過程と捉えられるかもしれません。健康な状態と比べれば、多くの病は体にとって負担やリスクになります。つまり、病気になるのを怖いと感じるのは、その先にある「死」という喪失体験が普段以上に想像されてしまうために、恐怖や不安が強くなるのかもしれないということです。
でも、 さんは相談内容に『楽に死ねる薬があるなら病気も怖くない』と書かれていました。また、【考えとは別の可能性】には「事故や突然死ぬこともある」と書かれています。この箇所は「病気になって苦しまずに死ぬこともあるかもしれない」という未来に対するポジティブな見方として理解をさせていただきました。つまり、 さんにとっての病気は「死」という喪失体験が喚起されることによる恐怖や不安ではなさそうということです。
では何に対する怖さなのか。相談内容には『当たり前に過ごせてることにありがたみを感じている反面ガンや病気でおじゃんになると思うとなんで死ぬまでこんなこと考えないといけないんだと思ってしまう』と書かれていましたね。
この記述から、 さんの現状には