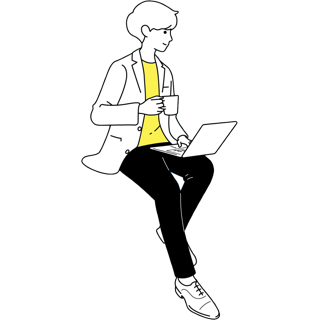「発達障害がありコミュニケーションが苦手だとカウンセラーは難しいのでしょうえか」の相談内容詳細
-
いまストレスを感じている「出来事」を事実ベースで抜き出してみてね。
「いつ・どこで・誰が・何を」を意識するのがコツだよ。
- 人と話している時(友達や大学の先生、バイト先の方やお客さん、家族など誰でも)、すぐに言葉がでなかったり吃ったり会話の腰を折る発言(遠回しすぎて内容が伝わりづらい、言いたいことが纏まっていないのに勢いにまかせて喋ってしまい何を言いたいのかわからなくなる)をしてしまいます。
何かの発表や注目される場面、大きな声を出す場面でなく、普段の日常会話のときになってしまいます。相手の話を聞いている時も、相手が言いたいことを汲み取れず、ズレた返事をしてしまうことも多いです。
私は小さい頃ADHDと診断され、施設の職員さんには「アスペルガーっぽいかな」とも言われていたようです。ADHDの特徴は小学校中学年あたりから落ち着き、そこから中学校1年生までは自覚している限りこの事について悩んだことはありません。
また、関係性はわかりませんが、中学校2年生の時に摂食障害になり中学校の殆どを入院して過ごしました。高校では病気が主な原因で友達を作れず、大学の1年〜2年の途中まではコロナの関係でオンライン授業という形を取られていたため人と話す機会がかなり少なかったです。
現在カウンセラーを目指して心理学を専攻して学んでいるにも関わらず、人とのコミュニケーションをうまくとれず、相手が何を伝えようとしているのか、お世話になっている先生方やバイト先の方、いつもの友達がどんな性格の子なのかすらよくわからない状態です。 - 「1」についての「感情」を%で表現してみてね。合計で100%にならなくても大丈夫。直感で書いてみよう。
- 情けなさ40%、申し訳なさ(気まずさ)30%、焦り20%、悲しさ10%
- 「1」について浮かんでいる「考え」を教えてね。
- せっかくみんなで楽しく話していても私の発言で場の空気を壊してしまうのが申し訳ないです。
特に一対一では話が噛み合っていないことと相手を困らせていることががよくわかります。本当は私も他の子が普通にできているような「会話が噛み合う楽しいおしゃべり」がしたいです。カウンセラーになるためにはそこからさらに相手の特徴や傾向、相手の様子から汲み取れる本心やもっと本質的な部分に気づき、その上で接する技術も必要になると思います。発達障害や精神疾患の病歴があるとやはり対人援助職は厳しいのでしょうか。
友達は本当にみんな優しくて、空気の読めない私を腫物扱いしたり煙たがったりすることなどなく、他の子同様に接してくれます。
友達ができたのが久しぶりだからか、緊張からか、テンションが上がってしまっているのか、どれだけ落ち着くように気をつけていても、話しているうちに冷静さが欠けてしまい自分の言動について客観視したり考え判断する前に言葉がでてしまいます。
発達障害や摂食障害の他にも、自分がその場の気持ちにのまれやすいこと、テンションが上がったり一度焦り始めると頭が真っ白になってしまうこと、物事を深く考えるのが苦手なことなど、自覚している問題はたくさんあるのにちゃんとできない自分が情けないし恥ずかしいです。
私は友達といて楽しいのに、私の方はそれを返すこともできず的外れな会話ばかりしてしまうことが嫌でたまりません。 - いろんな視点から捉えるために、上記の回答の「別の可能性」を考えてみよう。
- 引きこもり期間と人と話すことがほぼない期間が長かっただけで案外このまま人とコミュニケーションをとり続けたり滑舌を良くする努力をしたら解決しててくれないかな、と思います。
- いま専門家に聞いてみたいことは?
- どうしたら、相手の本質(人物像?)を理解できる、本心を汲み取ることができる、相手の気持ちに寄り添い共感できる、安心して話をしてもらえるなど心理士に必要な力を身につけることができますか。ここまで向いていない上に発達障害等があると無理でしょうか。
友達や学校の先生、バイト先でよくしてもらっている方たち等、わたしは本当に周りの人に恵まれていると思います。そういった人たちに(もちろんそれ以外の人にも)、わたしがそうしてもらったように、一緒に話していて楽しい、落ち着くと感じてもらいたいです。そうなるにはどうしたらいいですか。 - 年齢、性別、職業
- 21歳、女性、大学生
- 既往歴
- 発達障害(ADHD、アスペルガー)
摂食障害
APD - 悩みの内容の自由記述
- --- 未回答 ---
自分史はまだありません。
※ プライバシー保護のため、ご質問の一部を編集部で変更している場合がございます。
「発達障害がありコミュニケーションが苦手だとカウンセラーは難しいのでしょうえか」への回答
-
うさぎねこ さんへ、ご相談くださってありがとうございます。臨床心理士の浅井です。
コミュニケーションのとりかた、これは難しい悩みですね。人間は生きている限りほとんどコミュニケーションとりっぱなしですから、悩みは尽きないですよね。心理士を目指して勉強されているということで、自身の適性についての焦りや不安感もあるようにお見受けします。
早速ですが うさぎねこ さんを悩ませているものを切り分けていきたいと思います。書いていただいた文面からは、大きく2つの困りごとの姿が見えてきます。
①:コミュニケーションの苦手さに伴う情けなさや申し訳なさ(気まずさ)
②:心理士への適性がないかもしれないという不安や焦り少し乱暴なまとめに感じられるかもしれませんね。ですがこのように切り分けることで、複雑に絡み合った うさぎねこ さんのお悩みが整理していけるはずです。
まずは①の「コミュニケーションの苦手さに伴う情けなさや申し訳なさ(気まずさ)」から考えていきます。
うさぎねこ さんご自身も「考えとは別の可能性」のところで書かれているように、 うさぎねこ さんのコミュニケーションの苦手さの背景には、入院期間やオンライン授業といった環境的な要因も関連しているように思えます。そのため、コミュニケーションの経験を積んでいくことで解決されていく部分もあるでしょう。
ですがその「コミュニケーションの経験」を積むにあたって、情けなさや周囲の人への申し訳なさが足を引っ張ってしまうかもしれません。そこで1つ提案があります。