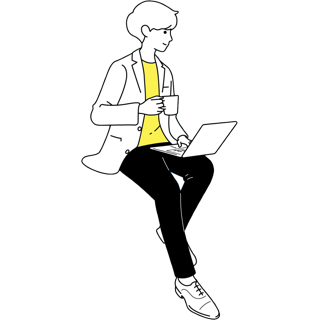「自分がされて辛かった親の対応を娘にもしてしまうのをやめたいです。」の相談内容詳細
-
いまストレスを感じている「出来事」を事実ベースで抜き出してみてね。
「いつ・どこで・誰が・何を」を意識するのがコツだよ。
- ほぼ毎日のように
家で育児をしていて
私がイヤイヤ期の娘に怒る時
(片付けをいやがる、要求がコロコロ変わるなど)
自分の幼少期に親からの対応で傷ついた場面(話をまともに聞いてもらえない、無視される、おかしいんじゃないの?と言われる、過度に怒られる)がフラッシュバックのように思い出されること - 「1」についての「感情」を%で表現してみてね。合計で100%にならなくても大丈夫。直感で書いてみよう。
- 怒り20%
焦り・不安60%
混乱40% - 「1」について浮かんでいる「考え」を教えてね。
- 上の子がイヤイヤ期で
何かにつけてイヤと言う。
まだ発達途中だということは頭では分かっていても
ただのワガママに見えることもあり
怒りが湧く。
自分のやりたいことが積み重なっているとき(掃除、洗濯、食事の用意など)や睡眠不足のときにはイライラしやすいと感じる。
また一日の中でも疲れが溜まってくる夕方に怒りがわきやすい。
そこで怒りが爆発して怒ってしまうと、声を荒げたりしている自分と
冷静に考えている自分がいる。
こんな風に怒ってしまって娘の心にも傷が残るだろうかという不安と
自分も幼い時こういう風に言われて悲しかったなとか
話しかけても無視されて辛かったなという光景がフラッシュバックしてくる。
なぜその場面が浮かんでくるのか分からず混乱している。
今まで生きてきてこんなに毎日のように誰かに怒ったことは無かったので人が変わってしまったように怒っている自分にも戸惑っている。
子どもを産む前のような穏やかな自分に戻りたいと毎日思うけれど
怒りやイライラの感情も毎日わきおこる。
その度にフラッシュバックもするし
娘も同じように心が傷付いたら?と不安。
でもどうしたらイライラせず済むのか、怒りの気持ちを切り替えられるのか分からない。
マインドフルネスも試したけれどうまくいかない。 - いろんな視点から捉えるために、上記の回答の「別の可能性」を考えてみよう。
- 3歳の子と7ヶ月の子を週6〜7日ひとりで見ているので怒りやイライラが出てくるのも当たり前。
頻度が多いのも当たり前かもしれない。
2人の夜泣きもまだあるので
まとまった睡眠時間が取れず
頭も働いていないのかもしれない。
娘の心に傷がつくかは
目には見えないから分からないけれどものの考え方は自分とは違うから何とも思っていないかもしれない - いま専門家に聞いてみたいことは?
- 自分が子どもの頃に傷ついたことを認め受け入れる
今ここを感じて怒りのピークが過ぎるのを待つ
iメッセージで伝える
など出来ることは多く試しましたが自分が幼い時に親からされて嫌だったこと(言い方や態度)を娘にもしてしまっている気がします。
そして何度もフラッシュバックしてしまうのが自分も苦しいです
でも他にどんな言葉でどんな態度で娘に伝えたらいいのかわかりません。
◎感情的に子どもに怒らないためには?
◎怒りや悲しみの感情を思い出さなくなるには?
◎冷静に気持ちを伝えたいときに意識できることは何かある? - 年齢、性別、職業
- 30歳、女、専業主婦
- 既往歴
- なし
- 悩みの内容の自由記述
- 2歳10ヶ月の娘と7ヶ月の息子がいます。とくにイヤイヤ期の娘に対して怒りの感情が出てしまうことが多いです。
実家は遠方のため今は年に数回会う程度です。
自分史はまだありません。
※ プライバシー保護のため、ご質問の一部を編集部で変更している場合がございます。
「自分がされて辛かった親の対応を娘にもしてしまうのをやめたいです。」への回答
-
rin さん、ご相談を寄せていただきありがとうございます。精神保健福祉士の中浦です。
3歳と7ヶ月のお子さんをほぼ毎日一人で見ていらっしゃるのですね。忙しく目まぐるしい日常を送っていることが想像できます。夜泣きがあって十分に睡眠が取れないと、いつもの自分でいることも難しくなってしまいますよね。
小さい頃に母親からされて傷ついた記憶に向き合いながら、イヤイヤ期の娘さんにかかわるのも、大きな苦痛を伴うものだと思います。
rin さんの過去から来る苦しみは一見個別性が高く見えますが、実は多くの人が同じような体験をされています。
今回の rin さんのお悩みを拝見し、ポイントは rin さんがお子さんのために頑張ろうとしている「方向」を変えることだと感じました。
具体的にいうと、自分にとっての良い親を目指すのではなく、子どもと自分を同一視しないために、もっと多様な親のあり方を知るということです。ひとつずつ説明していくので、どうぞお付き合いください。
rin さんは「赤ちゃん部屋のおばけ」という言葉はご存知でしょうか?
「赤ちゃん部屋のおばけ(以下おばけ)」は、児童精神科医であるフライバーグが、親が子どもと対面するとなぜか怒りや困惑が湧き上がり、自分で感情のコントロールをするのが難しくなる現象を見つけ、まるで「おばけの仕業」のように見えることから、このように名付けました。おばけとは、親が子どもと二人きりの場面において、「子どもが望むような養育ができていない」ことに対する罪の意識を植え付けようとしたり、望みを叶えてあげられない自分に対して「我が子が敵意を持っている」と恐怖の感情を抱かせようと悪さをする存在です。